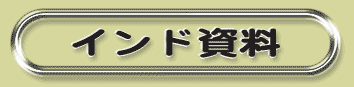 |
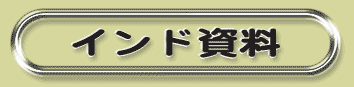 |
オリッサ州
|
ブバネーシュワル
|
カンダギリ、ウダヤギリ石窟寺院群
|
プーリー
|
コナーラクのスーリヤ寺院(世界遺産)
|
デカン高原
|
ナーガルジュナコンダ
|
アーランプル・ヒンドゥ寺院群
|
ハンピの都市遺跡(世界遺産)
|
バーダミ
|
アイホーレ
|
パッタダカルの寺院群(世界遺産)
|
ゴア
|