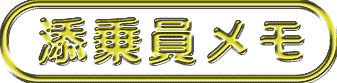
南インド・ドラヴィダ世界を行く 2月3日(月) 日本→クアラルンプール→チェンナイ 東京からマレーシア航空MH89便でクアラルンプール空港へ。夜の便で乗り継いでMH180便でチェンナイに向かう。チェンナイは1996年にマドラスから改称されたインド第4の都市で、空港も混雑していた。(タージコロマンデル泊) 2月4日(火) チェンナイ→カーンチープラム→チェンナイ チェンナイのマイラプール地区へ。マイラプールは‘孔雀の街’。チェンナイからマドゥライまでガイドはジャガンナート・バブーさんです。(Mr.Jagannath Babu)
国道4号線を走り、かつてのパッラヴァ朝の首都カーンチープラムへ。昼食後、観光。
帰り道の途中、シルク工場ではジャガート織機を使いサリーを織る様子を見学。その後ラジブ・ガンディーの暗殺現場を通りホテルへ。バラタ・ナーティアムを見ながらの夕食。 (タージコロマンデル泊) ◎バラタ・ナーティアム・・南インドの古典舞踊で108の形があり、元々はヒンドゥー教寺院内で伝承されてきた踊り。神、女神の恋愛物語が主にテーマで踊られる。2月5日(水) チェンナイ→マハーバリプラム→ポンディシェリー かつてパッラバ朝時代の海外交易の港町マハーバリプラムへ。
海岸寺院を眺めながら昼食、塩田が広がる道を走りポンディシェリーへ。ホテル近くのマーケットはお祭で熱気が溢れていた。 (アーナンダ・イン泊) 2月6日(木) ポンディシェリー→チダムバラム→ 土着の馬神を祀ったムニ寺院に立ち寄った後、チダムバラムへ。
昼食後、ガンガイコンダチョーラプラムへ。街の名の意味は‘ガンジス河を手に入れたチョーラ朝の王’。バスの中でケーランギーという南インドの繊維質の野菜を試食した。 ★ ブリハディーシュワラ寺院(シヴァ派/11世紀半ば/チョーラ朝) (ブリハディー・・大いなる神,シュワラ・・シヴァ神) ラージェンドラ1世がこの地をチョーラ朝の新しい都にした際、父ラージャラージャ王が建てたタンジャーヴ―ルの寺院と同名の寺院をここに造営。敬意を払い父王の寺院より大きくは造らなかった。寺院の一部は修復中で、午後の陽射しを浴びながら、11世紀と同じ手法で作業をする人々がいた。 美しいカーヴェリー河を渡り、クンバコナムへ。マハーマカム・タンクでは沐浴する様子も見られた。
その後タンジャーヴールヘ。この日もバラタ・ナーティアムを見ながらの夕食。ホテルの入り口でスタッフが写真撮影をしてくれた。 (パリシュータム泊)
2月7日(金) タンジャーヴール→ティルチラパッリ タンジャーヴールの観光。ホテルの前にエルカム・プーが咲いていた。茎から白い液体が出て、目に入ると失明するという花。インドでは殺虫剤として用いたり、香りのある花を嫌うガネーシャのために捧げる。(象は匂いのする花が嫌いだそうだ)
市内のオリエンタル・タワーホテル地下のスーパーで買物をして、昼食。昼食は南インド風のミールス。バナナの葉にご飯とカレー数種を盛り付けます。その後ティルチラパッリの手前、寺院都市シュリランガムへ。カーヴェリー河とコッリダム河に挟まれた中州で、ヒンドゥー教徒は中州を聖なる場所と考えます。途中ロック・フォートが見えた。
(サンガム泊) 2月8日(土) ティルチラパッリ→マドゥライ マドゥライに向けて午前中は移動の日。道路の両側にはタマリンドの樹が並び、また歯を磨くニームの樹で歯磨きに挑戦した。その他バナナや砂糖きび、やしの実畑が続く。バナナは一度実をつけると幹は切り倒し、その中の柔らかい部分はカレーにして食べるそうだ。途中やしの実でロープを作っている村を見学し、マドゥライへ。チェンナイに次ぐ南インド第2の都市です。
ミナ―クシ寺院近郊がバスの乗り入れができないのでオートリキシャーで移動し、少し街並もちがった目線で見えました。 (タージ・ガーデントリート泊)
2月9日(日) マドゥライ→パドマナーバプラム→カニャークマリ マドゥライからコーチンまでガイドはスレ―シュさん。(Mr.Suresh Kumar)本日も大移動の日で、昼食は風力発電所にてお弁当。パドマナーバプラムはタミルナドゥー州の飛び地で‘蓮の花から生まれた都’の意味。 ★ 王宮(15〜18世紀) かつてのトラヴァンコール藩王国の宮殿で、チーク材を使用したケララ様式の木造建築。トラヴァンコール藩王国はタミル語を話したので、現在でもタミルナドゥー州に組み込まれているが地理上ではケララ州にある。この王宮は夏の宮殿となったため度重なる戦乱にもあわず、きれいに今も残されることになった。 一路カニャークマリ(コモリン岬)へ。ベンガル湾、インド洋、アラビア海の合流するインド亜大陸最南端で、インドで唯一、太陽が海から昇り海へ沈む場所でもある。 ★ クマリ・アンマン寺院(18世紀/お寺の歴史はもっと古いとされる) クマリは土着の女神で、のちにパールヴァティと同一視されるようになった。クマリは処女の意味で、神々は処女である女神クマリの聖なる力(シャクティ)を守りたかったために、シヴァ神との結婚を邪魔したと言わる。彼女の鼻にはダイヤモンドのピアスが光り、沖にいる舟の漕ぎ手の目をくらまし転覆させてしまうという伝説に基づき、海に向いた扉はいつも閉められている。多くの巡礼者もいてゆっくり廻れないのが残念だった。 静かな海岸で夕陽を待ちました。今の時期はアラビア海に沈みます。海に沈む直前に雲に隠れてしまいましたが、きれいな姿を見せてくれました。 (シンガーインターナショナル泊)
2月10日(月) カニャークマリ→コーチン 夜明け前にホテルを出発、岬の最南端近くで日の出を待つ。雲があり、海から昇る朝日は見えなかったが、6時半過ぎにベンガル湾からお天道様が雲間から顔を出した。元旦でもないのに毎日こんなに多くの人々が朝日を待つ光景には驚かさる。最南端ポイントやガンディー記念堂を歩いて、ホテルへ。朝食後、コーチンへ向けての大移動。田んぼにはたくさんの白鷺が飛び降り、蓮池からは花が咲き美しい光景が広がる。途中、ケララ州に入るとスカンダ寺院のお祭の行列に出会った。象や子供の頭に担がれた壷にはターメリック水が入っていて、プージャー(お祈り)の時に使うとのこと。ティルヴァナンダプラム(旧トリバンドラム)にて昼食。近くの寺院に立ち寄った。 ★ スリ・パドマナーバスワミ寺院(ヴィシュヌ派) 白いゴープラムが印象的な寺院。トラヴァンコール藩王国独特の風習で、寺院に入る前には寺院前に広がる池で沐浴をして男性はドーティ、女性はサリーで正装してから入場するそうだ。 途中クイロン先のホテルで、南インドならではのコーヒーと揚げバナナを食べた。夕方バスを海岸近くに停め、沈みゆく夕日を眺めた。この日は水平線にお天道様が帰っていくところまで見送ることが出来た。長い移動の一日お疲れ様でした。 (タージレジデンシー泊) 2月11日(火) コーチン市内観光 コーチンは昔からの町オールド・コーチンと、並行する人工の島ウィリンドン島、18世紀以降の町エルナクラムの3つの部分から成り立っている。オールド・コーチンはフォート・コーチン地区とマッタンチェリー地区に分かれている。ケララ州のケラはやし、ラは国を意味し、いたるところにやしの木々が見られた。
夕方、ケララ文化センターにてカタカリ・ダンスを見学。今夜は「ヴァガバット・ギーター」より‘王と美女’のお話。村のカタカリは、数人の役者が交代で夜9時頃より翌朝まで踊り続け、お化粧には3時間かかるそうです。 (タージレジデンシ―泊) 2月12日(水) コーチン→バンガロール→マイソール 朝、ジェットエアウェイズ9W3512便でコーチンからカルナータカ州のバンガロールへ。バンガロールはインドのシリコンバレーと呼ばれ、コンピューター産業が盛ん。標高が約900mで年間通して過ごしやすいところで、避暑地としても有名。バンガロールのガイドはラメーシュさん。(Mr.Ramesh)
カルナータカ州政庁のヴィダーナ・サウダを通り、ホテルで昼食。古都マイソールへ向かう途中で砂糖きび工場を見学。黒砂糖はジャグリーと呼ばれ、砂糖きびを搾り、大きな鍋を熱して作業していた。味見したジャグリーは素朴な味がした。 (クオリティ・イン・サザンスター泊) 2月13日(木) マイソール→シュラヴァナベルゴラ→ハレビート→ ★ ゴーマテシュワラ像(981年) 143mの巨大な花こう岩の丘・インドラギリ(雷神の丘)の618段の階段を登ると、高さ18mのゴーマテシュワラの像がある。ジャイナ教初代祖師の息子ゴーマテシュワラは、ジャイナ教24聖人のうちの1人で、裸で12年間直立不動のまま瞑想し、その体にはつたが絡んでいる。12年に一度、この像を清める大きなお祭りがあり、次は2005年だそうだ。 丘のうえからの景色は素晴らしく、階段を登った苦労を忘れるほど。寺院の下でこの地方でよく見かけるジャック・フルーツを試食した。ハッサンの街で昼食後、12〜13世紀にマイソール地方で栄えたホイサラ朝の首都・ハレビートへ。 ★ ホイサレーシュワラ寺院(シヴァ派/12世紀) (ホイ・・殺す,サラ・・男の子の名前,シュワラ・・シヴァ神) 1127年にホイサラ朝の王ビッティガ(ヴィシュヌヴァルダナ)とその妃チャンタレ専用のヒンドゥー寺院として建立したため、寺院内には2連の本殿とナンディー像がある。せっけん石(緑色結晶片岩)を使用した細かい彫刻が美しい寺院。踊るガネーシャを乗せ、枠に指が食い込んで痛そうなネズミなどユーモラスな彫刻がたくさんあった。
次にハレビートと並ぶホイサラ朝の都ベルールへ。 ★ チェンナ・ケーシャヴァ寺院(ヴィシュヌ派/1116年) (チェンナ・・美,ケーシャヴァ・・ヴィシュヌ神) ホイサラ朝の王ヴィシュヌヴァルダナが隣国チョーラ王朝との戦いに勝った戦勝記念のために建てた寺院で、本尊は女性の姿をしたヴィシュヌ神。寺院の枕木の部分に施された女性の彫刻はとても精緻で、一人一人の髪型も違っている。 長い帰り道でしたが、真っ赤な夕日が車窓から見えた。 (クオリティ・イン・サザンスター泊) 2月14日(金) マイソール→ソムナートプル→ ★ ケーシャヴァ寺院(ヴィシュヌ派/13世紀) 1268年から40年間かけて建てられたホイサラ様式の最高傑作と言われる寺院。1つの寺院に3つの祠があり、16の円形天井が完全な姿で残っている。天井にはマンゴーの葉とバナナの葉を組み合わせた彫刻や、牛の足跡を模様にしたものなど想像に富んでいた。神々はこの寺院を欲しがり寺院自体が宙に浮いたため、彫刻師はわざと一部の彫刻を壊し防いだというほど美しい彫刻が残っている。 マイソール王国のティプー・スルタンがイギリスと闘って壮絶な戦死を遂げた城塞都市のシュリランガパトナムへ。 ★ ダリヤ・ダウラトバーグ宮殿(1782年/ティプー・スルタン建設) (ダリヤ・・海,ダウラト・・勝利,バーグ・・庭) 1780年にカンチープラム近くの英国人との戦争で勝利し、南インドのベンガル湾〜アラビア海までの領土を手にした記念にこの名をつけて建設。ここへティプー・スルタンは夕涼みに来たそうだ。マイソール戦争の模様が壁画に描かれていた。 シュリランガパトナムは中州にある都市で、昼食のホテル裏にはカーヴェリー河が流れていた。ここからバンガロールへ戻り、夕食後空港へ向った。 2月15日(金) バンガロール→クアラルンプール→成田空港 バンガロールからMH193便にてクアラルンプールへ向かい、朝のMH70便で乗り継いで成田空港へ。最後の長い移動、皆様大変お疲れ様でした。最後にこの度は「南インド・ドラヴィダ世界を行く」にご参加いただき誠にありがとうございました。今後ともS旅行をよろしくお願い申し上げます。またいつか、皆様にお逢いできる日を心待ちにしております。
南インド・ドラヴィダ世界を行く 2003年2月3日〜2月15日 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||